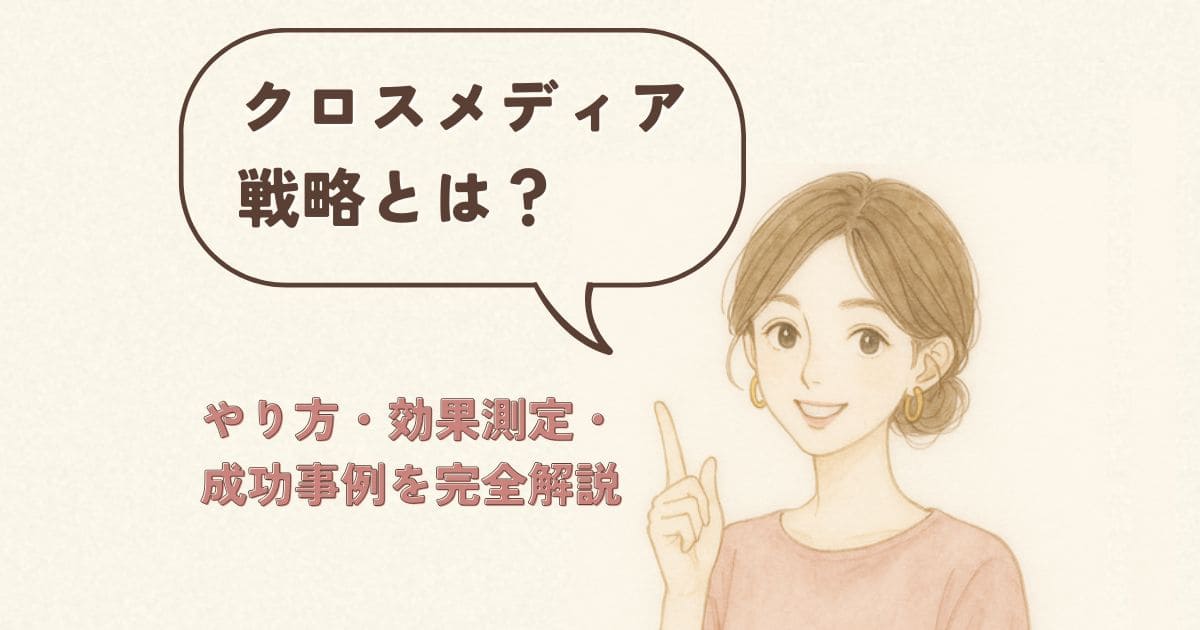
クロスメディア戦略とは?意味と重要性を解説

![]()
クロスメディア戦略って何…?
クロスメディア戦略の基本
クロスメディア戦略とは、複数の異なるメディア(テレビ、新聞、Web、SNSなど)で一貫したメッセージをユーザーに届け、広告効果を最大化する手法です。単なる広告の同時配信ではなく、メディアごとの特性を活かして相乗効果を狙う点が大きな特徴です。
総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査(2024年版)」によると、1人あたりのメディア接触時間はデジタル・マスの合計で1日5時間に達しています。ユーザーの情報接触チャネルは分散しており、単一メディアでは接触機会を取りこぼすリスクが高いことが分かります。そのため複数媒体を連携させて相乗効果を引き出す「クロスメディア戦略」の必要性が高まっています。
- 【各メディアの特徴】
- ■テレビやラジオ:広範囲へのリーチに強い
- ■Web広告:ターゲティング精度が高い
- ■SNS:エンゲージメントや拡散性が高い
クロスメディア戦略の価値は、メディアごとの利点を掛け合わせて、全体としての広告効果を最適化できる点にあります。
なぜクロスメディア戦略が必要なのか?
クロスメディア戦略が求められる理由は、単なるトレンドではなく時代の流れと技術革新、そして消費者の行動が変化しているからです。ここでは、その背景を3つの観点から詳しく解説します。
![]()
1. デジタル技術の発達と情報チャネルの多様化
スマートフォンの普及とともに、ユーザーはテレビ・新聞・雑誌といったマス媒体だけでなく、Web、SNS、動画媒体、アプリ、デジタルサイネージ、メルマガなど複数の接点を横断しながら情報収集・購買判断を行うようになりました。
この変化は2000年代に加速し、2010年前後のスマートフォン普及で決定的になりました。結果として、企業は単一媒体への依存するのではなく、メディア間の連携を前提としたクロスメディア戦略が求められるようになっています。
年代別にみるクロスメディア定着の流れ(ユニクロの事例)
2000年前後:TV×新聞折込で「機能/デザイン×価格・在庫」を訴求
- ユニクロ(〜2000年):大量販売期(フリースブーム)には、テレビCM等で商品イメージ・機能性を訴求しつつ、新聞折込チラシで「価格・カラー展開・在庫情報・期間限定値下げ」など即時性の高い情報を補完する組み合わせが主流でした。このような手法は、マス×店頭起点の連携を示す代表例です。
2003〜2006年:機能素材の台頭と「機能価値×マス露出×店頭」の同期
- ユニクロ×東レ(2003年〜):2003年の「HEATTECH」発売により、機能性訴求を軸にTVや店頭、後年はオンラインにも広がる“キャンペーン同期”が一般化しました。素材メーカーとの共同開発による機能価値を、マス広告と売場体験で一体的に伝える設計が定着しました。
2007〜2008年:デジタル起点のグローバル拡散と店頭連動
- UNIQLOCK(2007〜2008年):ブログパーツ・スクリーンセーバーなど“生活導線に溶け込むデジタル接点”を世界へ配布し、店頭インスタレーションとも連動させました。カンヌ国際広告祭でグランプリを受賞し、デジタル×店頭×グローバルPRのクロスメディア象徴事例になりました。
2010〜2014年:スマホ普及で「紙×モバイル×EC」を直結(O2Oの本格化)
- スマホ普及の臨界点:日本では2008年のiPhone登場以降、スマホ利用が急増しました。2010年代前半にモバイルが購買・来店の主導接点となり、紙媒体や店頭との橋渡し役になりました。
- ユニクロ「チラシスキャン」(2014年):新聞折込・店頭配布のチラシをスマホで読み取り、そのままオンラインストアのカートへ追加できる施策を開始しました。紙→モバイル→ECの一気通貫を実装し、紙媒体を“購買機能付きメディア”に拡張させました。
2015年以降:アプリ/SNS/デジタルサイネージ×紙チラシのハイブリッド運用
- ユニクロのスタンダード運用:TV・オンライン広告で新商品の機能価値を広域に告知しつつ、アプリ/メール/SNS/新聞折込チラシで“期間限定価格”や在庫・カラーなどの購入意思決定情報をタイムリーに配信しています。現在でも、実店舗・EC・アプリ会員基盤を横断させる運用が中心です。
ユニクロの例でも分かるように、ユーザーは一つのメディアだけで商品やサービスと接触することが少なくなり、複数メディアを横断しながら意思決定するようになりました。そのため、企業側も一つのメディアに依存した広告展開ではなく、媒体間の相互連携を前提としたクロスメディア戦略が必要になっています。
2. 消費者行動モデルの変化
消費者行動モデルにも大きな変化が生じています。かつての消費者行動モデルはAIDMA(注意(Attention)→興味関心(Interest)→欲求(Desire)→記憶(Memory)→行動(Action))が主流でしたが、現在ではより複雑なモデルが登場しています。
- AISAS:注意(Attention)→興味関心(Interest)→検索(Search)→行動(Action)→共有(Share)
- AISCEAS:注意(Attention)→興味関心(Interest)→検索(Search)→比較(Comparison)→検討(Examination)→行動(Action)→共有(Share)
AISASモデルやAISCEASモデルは、検索・比較・検討・共有などのステップが加わっているため、プロモーションを行う際に「見せる」だけでなく「調べてもらう」「納得してもらう」「共感してもらう」ことまで意識する必要があります。クロスメディア戦略は、各段階に適したメディアとコンテンツを設計することで、ユーザーの購買意思決定プロセス全体にアプローチすることができます。
3. 広告効果測定の精度向上とROI重視の時代
近年では、GoogleアナリティクスやSNS広告の登場により、広告の効果を定量的に測定できる環境が整いました。これにより、従来はあいまいだった広告費対効果(ROI)を明確に可視化できるようになり、「数字で語れるマーケティング」が強く求められています。
クロスメディア戦略は、各メディアごとのKPIだけでなく、媒体間の連携による相乗効果も測定対象とすることで、広告全体の最適化と費用対効果の向上を目指すことができます。
上記の背景から、現代のプロモーション活動では「単に複数メディアへ広告を出稿するだけ」では不十分で、ユーザーの行動・購買プロセスに基づいたメディア連携と設計が不可欠です。クロスメディア戦略は、まさにこの変化に適応するための根本的な解決策であり、これからのマーケティングを成功に導くカギを握っています。
メディアミックスとの違い
クロスメディア戦略と混同されがちなのが「メディアミックス」です。メディアミックスとは、複数のメディアを掛け合わせて、プロモーションやコンテンツ展開を行う戦略のことです。両者とも複数メディアを活用する点では共通していますが、アプローチと設計思想に明確な違いがあります。
![]()
クロスメディアとメディアミックスの違いは?
| 項目 | クロスメディア戦略 | メディアミックス |
|---|---|---|
| 目的 | 一貫した体験・メッセージを通じて行動を促す | 広く認知を拡げる |
| 設計思想 | メディア間の連携・導線を重視 | 個別メディアの特性を活かす |
| 測定指標 | KPIで効果を統合的に管理 | 各メディアごとの成果測定が中心 |
| 代表例 | Web広告やSNSでの認知拡大→リアルイベントにつなげる | テレビCMと新聞広告を同時出稿 |
違いを正しく理解することで、マーケティングの設計はより精度が高まります。目的に応じて適切な手法を選ぶことが、効果的なプロモーションの鍵です。
クロスメディア戦略の成功3ステップ

![]()
戦略は立てたのに、成果につながらない…
①ペルソナ設定とターゲット分析
クロスメディア戦略の出発点は、「誰に届けるか」を明確にすることです。そのためにまずは、ターゲットとなるユーザーの行動や価値観を具体的にイメージした「ペルソナ」の設定が重要です。
このステップを曖昧なまま進めてしまうと、広告の内容や配信先がバラバラになり、期待される効果が得られなくなります。
- ■ペルソナの設定内容
- ・年齢・性別・職業・年収などの基本属性
- ・日常の行動パターンや情報接触チャネル(通勤中にスマホでSNSを利用する、週末は家族とテレビ視聴など)
- ・商品・サービスに求める価値観
これらの要素を組み合わせて作成されたペルソナを軸にすることで、メディア選定や広告内容の整合性が取りやすくなり、戦略全体がブレなくなります。
②カスタマージャーニーの設計
ペルソナを設定した後は、その人物が購買に至るまでのプロセスを描く「カスタマージャーニーマップ」を設計します。これは、ユーザーがどのような接点で何を感じ、どんな行動を取るのかを時系列で整理するものです。
カスタマージャーニーを可視化することで、ユーザーが各段階で必要とする情報や適切なメディアを把握できます。
![]()
- 認知段階:テレビCM、SNS広告、Webバナーなど
- 興味・比較段階:比較サイト、オウンドメディアの記事など
- 行動段階:リターゲティング広告、限定オファーLPなど
適切なメディアで最適なタイミングにメッセージを届けることができれば、ユーザーの行動を自然に導くクロスメディア設計が可能となります。
③KPI設定と高度な効果測定・PDCA運用
最後のステップは、戦略が効果的に機能しているかを測定・改善するための仕組みを構築することです。KPI(重要業績評価指標)を設定し、PDCAサイクルで継続的に改善を行うだけでなく、より高度な分析手法を取り入れることが成果最大化の鍵となります。
| KPIの例 | 目的 | 測定・分析手法 |
|---|---|---|
| Web広告のクリック率 | ユーザーの興味・関心度を測る | Google広告/Yahoo広告+アトリビューション分析 |
| ブランド名の検索数 | 認知度の向上を可視化 | Googleサーチコンソール+クロスデバイストラッキング |
| CVR(コンバージョン率) | 最終成果につながるアクション率を可視化 | Googleアナリティクス+マルチタッチアトリビューション |
高度な効果測定手法の具体例
- アトリビューション分析:どのチャネルが成果にどの程度寄与したかを可視化。
例:ファーストタッチが「テレビCM」、ラストタッチが「リスティング広告」の場合、両者の貢献度をどのように配分するかを数値化。 - マルチタッチアトリビューション:顧客が複数チャネルに接触した際、それぞれの接点に適切な重みを配分。ラストクリックだけに依存しない、より実態に近い評価が可能。
- クロスデバイストラッキング:ユーザーがスマホで広告を見てからPCで購入するようなケースを把握。デバイスを跨いだ行動を正しく測定することで、施策の全体像を捉えられる。
重要なのは、単なる定量的なKPIモニタリングにとどまらず、各チャネルの「貢献度」を精緻に把握し、改善を続ける体制を整えることです。分析と改善を繰り返すことで、クロスメディア戦略の精度とROIは飛躍的に向上します。
クロスメディア戦略のメリット3選

![]()
クロスメディア戦略のメリットは?
接点の拡大による認知向上
クロスメディア戦略の最大の強みは、ユーザーとの接点を広げられる点です。テレビやラジオ、Web広告、SNS、チラシなど、ユーザーが接する複数の媒体を活用することで接触回数が増え、ブランドや商品への認知が高まります。
特に現代は、メディアの利用が細分化されているため、1つのメディアだけで全ユーザーにリーチするのは難しいです。
- ■ターゲットとリーチしやすいメディア
- ・若年層:Instagram・YouTube・X(旧Twitter)
- ・ビジネス層:ニュースアプリ・ビジネスメディア・LinkedIn
- ・高年齢層:テレビ・新聞・地域情報誌
このように、ターゲットごとにプロモーションするメディアを検討するすることで、より広範囲なユーザーにリーチできます。
一貫したメッセージ伝達
クロスメディア戦略では、どのメディアでも同じメッセージを届けることが重要です。これにより、情報の矛盾がなくなり、ブランドに対する信頼が高まります。
一貫性のある情報発信は、ユーザーに安心感を与えるだけでなく、記憶にも残りやすく、ブランドの世界観を強く印象づけます。
- ■クロスメディア戦略の注意点
- ・テレビCMでもWeb広告でも同じキャッチコピーを使用
- ・ビジュアルトーンや色味を統一
- ・Webサイトと広告でメッセージの整合性を取る
この一貫性こそが、クロスメディアならではのブランディング力につながります。
購買行動を後押しする効果
クロスメディア戦略は、複数のメディアでユーザーの購買行動を後押しします。たとえば、テレビCMで商品に興味を持ったユーザーが、Web広告で再び接触し、公式サイトで詳細を確認するという流れです。
| メディア | 主な役割 | 効果の一例 |
|---|---|---|
| テレビCM | 広域リーチ・認知拡大 | ブランド想起の向上 |
| SNS | ユーザーとの接点強化 | 拡散・口コミ効果 |
| Web広告 | 行動喚起・再アプローチ | CV促進 |
クロスメディア戦略を適切に検討することで、自然な流れでユーザーをコンバージョンまで誘導できます。
クロスメディア戦略の成功事例

![]()
他社はどうやって成果を出しているのか気になる…
メディア活用の工夫と効果
クロスメディア戦略の効果を高めるためには、各メディアの特性を活かしたコンテンツ制作と配信が重要です。たとえば、テレビCMでは視覚と聴覚に訴えるストーリー性のある映像を提供し、Webサイトでは詳細な製品情報やキャンペーン情報を掲載、SNSではユーザー参加型のキャンペーンを実施するなど、メディアごとの役割を明確にすることが重要です。
- テレビCM:ブランド認知の向上
- 広範な視聴者へのアプローチ
- 感情に訴えるストーリーテリング
- Webサイト:詳細情報の提供
- 製品スペックや価格情報の掲載
- 購入や問い合わせへの導線設計
- SNS:ユーザーとのエンゲージメント強化
- キャンペーン情報の拡散
- ユーザー生成コンテンツの活用
たとえば、「アサヒスーパードライ」のキャンペーンでは、テレビCM・駅構内の交通広告・SNS広告・デジタル動画広告を連携させたクロスメディア戦略を展開しました。
ユーザーはテレビCMでブランドを認知し、駅での大型広告で印象を強化。さらに、SNSでコンテンツに触れ、Web動画で商品理解を深めた上で購買へと至る流れを設計しています。
- テレビCM:全国的な認知を確保
- 交通広告:移動中の接触機会でブランド想起
- SNS広告:ターゲット世代への再アプローチ
- Web動画:製品理解とエンゲージメント強化
このように、媒体ごとの特性を活かして戦略を組み立てることで、一貫したブランド体験を提供し、購買行動を促進することができます。
成功事例の共通点
クロスメディア戦略が成功している事例にはいくつかの共通点があります。
| 共通項目 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 明確なターゲット設計 | ペルソナに基づいた企画 | 広告の最適化と無駄の削減 |
| メディア連携の導線設計 | メディアをまたぐユーザー導線 | 接触回数の増加と認知強化 |
| 一貫性のあるメッセージ | 全メディアで同じ世界観を表現 | ブランド信頼度の向上 |
| データに基づく検証と改善 | KPIとPDCAを活用 | 継続的な成果向上 |
これらの要素を意識して設計することで、自社に合ったクロスメディア戦略の構築と効果最大化が可能になります。
メディア選定とクロスメディア戦略の最適化

![]()
トリプルメディアの使い分け
クロスメディア戦略の要となるのが、トリプルメディアの適切な活用です。トリプルメディアとは「ペイドメディア」「オウンドメディア」「アーンドメディア」の3種を指します。それぞれの役割と活用法を理解することで、メディア戦略を最適化できます。
| メディア種別 | 特徴 | 役割 |
|---|---|---|
| ペイドメディア | 広告枠を購入して露出を増やす | 即効性のある認知拡大 |
| オウンドメディア | 自社が所有するメディア(HPやブログ) | 情報の蓄積と信頼性の構築 |
| アーンドメディア | SNSなどでのユーザー発信・口コミ | 共感・拡散による信頼獲得 |
この3つを状況に応じて使い分けることで、ターゲットとの接触を自然に増やすことができます。
最適なメディアの選び方
最適なメディアを選ぶには、ターゲットの生活行動と情報収集方法を考える必要があります。メディアごとの利用傾向を分析することで、効果的な選定が可能になります。
- 若年層:SNSやYouTubeなど動画・スマホ中心
- ビジネス層:検索エンジン・ニュースメディア
- 中高年層:テレビ・新聞・チラシなど紙媒体
また、商品・サービスの特性も重要です。商品の使い方など詳細な訴求が必要な場合は動画広告、信頼性を訴求したい場合はマスメディア広告など、伝えたい内容と手段の整合性も考慮しましょう。
メディア間連携のポイント
クロスメディア戦略で成果を上げるには、メディア間の連携を考慮しなければなりません。単に複数メディアを使うだけではなく、それぞれのメディアが相互に機能するよう設計することが重要です。
![]()
具体的にはどうすれば良いの?
- ・同じクリエイティブ(色、ロゴ、メッセージ)を使用して統一感を出す
- ・テレビなどのマスメディアで広く認知拡大→SNSでユーザー参加型のキャンペーンを実施
- ・共通のランディングページを活用し、データ集約と分析を可能にする
このように導線設計と、統一感のあるクリエイティブ展開がクロスメディア戦略の成功には欠かせません。
よくある質問(FAQ)

クロスメディア戦略とは何ですか?
クロスメディア戦略とは、複数の異なるメディアを連携させ、一貫したメッセージをユーザーに届ける広告・プロモーション戦略です。
テレビCM、新聞広告、Web広告、SNSキャンペーンなど、異なる媒体を組み合わせて活用することで、単体では得られない相乗効果を生み出し、認知向上から購買促進まで幅広い効果を狙います。
クロスメディア戦略は、情報が多様化しメディア利用が分散する現代において、必要不可欠なマーケティング手法です。
クロスメディアの具体例は?
クロスメディア戦略の具体例には、以下のようなパターンがあります。
| 目的 | メディア組み合わせ | 具体的施策例 |
|---|---|---|
| 認知拡大とエンゲージメント向上 | テレビCM+SNS広告 | テレビで商品認知→SNSで限定キャンペーンを告知 |
| 購買意欲の促進 | 新聞広告+Web広告 | 新聞で話題喚起→Webで詳細情報に誘導 |
| 行動喚起と来店促進 | 屋外広告+アプリ通知 | 交通広告で注目→アプリから割引クーポン配布 |
メディアをまたいで情報を連携させることで、ユーザー体験を高めることが可能です。
メディアミックスとクロスメディアの違いは何ですか?
メディアミックスとクロスメディア戦略は似ていますが、目的とアプローチに明確な違いがあります。
- メディアミックス:異なる媒体を同時に活用して、認知拡大を狙う手法
- 例:テレビCMとラジオCMを同時に流す
- それぞれの媒体の強みを活かすが、連携は薄い
- クロスメディア戦略:異なる媒体を連携させ、一貫したストーリーでユーザーを導く手法
- 例:テレビCMで認知→Webで比較検討→SNSで購買促進
- 各メディアが連動してユーザーの行動を促す
まとめ:クロスメディア戦略の実践ポイント

![]()
結局、何から始めればいいの…?
ユーザー理解と全体設計
クロスメディア戦略を成功させるために、まずはユーザー理解が最優先です。ターゲットがどのメディアを使い、どんな情報に反応し、どのように購買に至るのかを深掘りすることから始めます。
その上で、個別の広告施策ではなく、ユーザーの行動導線を軸にしたメディア配置を設計します。これにより、広告の接触から購買までの流れに一貫性を持たせることができます。
- ■クロスメディア戦略のポイント
- ・ペルソナ設定とカスタマージャーニーの可視化
- ・各メディアの接点に応じた役割設計
- ・ブランドメッセージの統一
社内体制と実行力の強化
どれだけ優れた戦略を描いても、実行する力がなければ成果は出ません。クロスメディア戦略は複数部門の連携が不可欠なため、社内での情報共有や役割分担の明確化が求められます。
- ■社内体制と実行力の強化
- ・マーケティング・営業・制作など部門横断のチーム構築
- ・進行管理と情報連携のためのプロジェクト体制整備
- ・外部パートナー(広告代理店など)との連携強化
特に、広告代理店へ依頼する際は、運用方針の明確化とPDCAサイクルの実施が成果のカギとなります。
最適なチーム体制と仕組みを整えることで、戦略を確実に実行し、最大限の成果を引き出すことができます。
今回の記事が、クロスメディア戦略を検討しているWeb担当者・マーケティング担当者の方の参考になれば幸いです。最新のトレンドや成功実績に基づいたマーケティング戦略の立案を依頼したい場合は、シーエムスタッフまでご相談ください。業種や商品・サービス問わず、各企業様に最適なご提案をさせていただきます。
資料ダウンロード
シーエムスタッフの会社紹介・サービス紹介資料と、運用事例がギュッと凝縮された資料を無料で提供しています。





